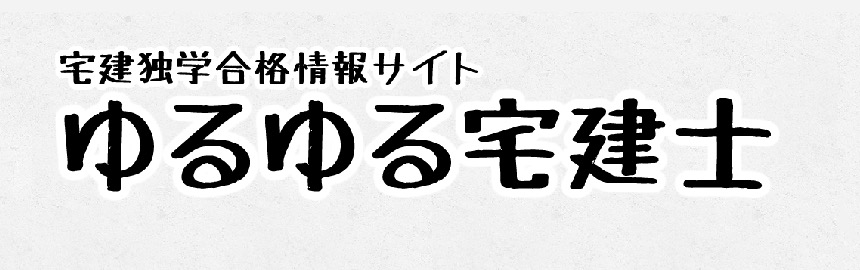宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。
- Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。
- Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。
- AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。
コメント
「自ら売主」この言葉が、私あんまり理解できませんでしたので、解説を・・・
この「自ら売主」ってのは、なんぞ?ということなのですが、いわゆる、「売主宅建業者」なんですね。つまり、媒介と比べて「宅建業者自らが売主」の場合という意味です。変な言葉ですね。もっとわかりやすく「宅建業者が売主の場合」って言えばいいのに、「みずからうりぬし」とかいう言葉を使っています。
で、この「みずからうりぬし」という言葉が出てくると、どうなるか?なんですが、
特殊な制限が働くということなんです。この制限が8つあります。これを「8つの制限」とか、「8種制限」とか言います。
他人物売買の禁止
クーリングオフ制度の適用
損害賠償の予定額と違約金の合計を売買代金の2割以下にする制限(第38条)
手付は解約手付とし売買代金の2割を超える手付金の受領を禁止する制限(第39条)
民法よりも買主に不利となる瑕疵担保責任の特約の無効(第40条)
保全措置を講じないまま一定額以上の手付金等を受領することの禁止(第41条、第41条の2)
割賦販売契約の解除と割賦金の残金の請求は30日以上の期間を定めた上で書面で催告を行っても買主側から支払いが無い場合に限り実施できる制限(第42条)
所有権を留保したままの売買契約と引き渡し後の譲渡担保の禁止(第43条)
この8つです。
このテーマは特に出題されますので、しっかり過去問解いてパターンを身につけましょう。
ちなみに、「売主=宅建業者、買主=宅建業者」の場合は、8つの制限かかりません。なんでか・・・素人買主保護目的だからですね。
で、本問では、
A=宅建業者(売主)
B=宅建業者でない(素人買主)
と定義されています。
肢 1
Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。
A・・・宅建業者(売主)
B・・・ 宅建業者でない(素人買主)
問題を整理しましょう。
C(元の所有者) → A(業者:売主) → B(素人)
こんな図式です。
これは、他人物売買の話ですね。
他人物売買の要点を整理すると、宅建業者は、他人の土地を勝手に売れませんよという制限です。
あれ、宅建業者でなくても他人の土地ってうっちゃならないのでは?と思いました?
実は・・・民法では、OKなんです。
売れちゃうんです。びっくりしました?というのは、もちろん他人の土地なんで最終的に名義変更まで行くかどうかはありますよ。多分行かないでしょうけど、例えば、「親父から貰う土地やねん、もう契約しとこうか!」としても契約は有効なんです。契約を優先するんですね。でも、トラブルになるんじゃ?と思った方は正解です。トラブルになる可能性はあります。そんな時は、「違約金」とか「損害賠償」とかでカタをつけます。
でも、宅建業者の場合は、そんな最初からトラブルになるような契約は無効だよと制限かけています。
そういう話なんですね。
でも、少し条件があって、「ちゃんと契約していれば、条件なしの契約をしていれば他人物でもOK」というのがあります。
ちゃんと契約していれば、エンドの素人さんには迷惑かからんだろうという話です。でも、「条件付き契約」なんかでは、ダメですよとなっています。
さて、問題ですが、
あれ、解説分そのままですね。でも括弧の中身が・・・
(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)
一定の条件が付されているって・・・だめじゃんか。
これは、契約できません。
ということで、
答え:「一定の条件が付されている契約をしている他人物を素人相手に契約できる 」わけではないので、「✖︎」
ですね。
肢 2
Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。
これは、瑕疵担保責任についてですね。
「建物の引渡しの日から1年間とする」瑕疵担保責任は無効となるけども、「瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる」か?!
という話です。
さて、解説ですが、
まず、瑕疵担保責任についてですが、
一般の取引の場合
買主さんが家を買いました。雨漏りがあるとは聞いてなかった。そんな場合どうなるのでしょうか?売主の責任ってあるの?
はい、あります。
ですので、一般の売主の場合、瑕疵担保責任は負いませんとか、3ヶ月間給排水とかつけるのが一般的です。
一応買主保護です。でも、売主さんも素人さんなんでわからない場合も多いです。でも、わかっている雨漏りとかは、隠れた瑕疵に入りません。あくまでのわからなかったという時の話です。皆さんも売主になった時は、わからないことでも先に言っておくことが必要です。先に言っておきさえすれば隠れた瑕疵になりません。実際隠れた瑕疵がわかった時はどうなるのでしょうか?
発見から1年間以内にいうことで有効になります。1年すぎると適用外です。何ができるかというと、損害賠償できたり契約を解除できたりします。怖いですね。10年経ってもですよ。
ここは、民法の範疇です。
でも、宅建業者が売主の場合は、責任が発生します。
よく見かけませんか?「瑕疵担保責任2年ついています!」という文言を。
しかし、あれば間違いです。
業者つまり、プロが売主の場合、素人売主にはつけられた「瑕疵担保責任なし」という特約がつけることができません。
なぜか?
プロが売主で、「瑕疵担保責任なし特約」つけられて、フタ開けたらボロボロの物件を買わされたらどうでしょうか?
泣き寝入りですね。
その泣き寝入り防止のためにこの法律はあります。
つまり、業者が、買主素人や「瑕疵担保責任なし特約つけたれ!」と言っても、無効になります。
で、その場合どうなるのか?
はい。
「発見から1年間」という民法が適用されます。
10年経っていても、発見から1年間です。20年経っていても発見から1年間です。
おそろしいですね。
で、そしたら、業者は全て発見から1年間という一番厳しい基準になるのか?というとそうでもありません。
特例があります。
「引き渡しの日から2年間」という期限付きで瑕疵担保責任打ち切りができるのです。
ですので、「引き渡しから2年間」というのは、当たり前田のクラッカー的なことなんです。
で、本問にもありますように、「引き渡しから1年は瑕疵担保責任受け付けます」という特約は無効になります。
しかし、その無効がなくなったからといって、「引き渡しから2年間」に延長されるのでしょうか?!
いいえ、そうではありません。この特約自体が無効となり、「発見から1年間」の民法が適用されることになるのです。
業者からしたらゴギャーン!という感じですね。
ですので、最低2年なのです。勘違いしてはいけません。
ということで、
解説が長くなりましたが、
答え:「引き渡しの日から2年になる」わけではないので「✖︎」ですね。